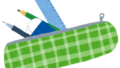まさかぶららが自分に一目惚れしていたとは!
助態の淡い期待は即否定された。
「あ、いや。勘違いさせたんならごめん。助態が好きなんじゃなくて、助態に見られているのが好きなんだ。」
そう言ってぶららは自分の足元に視線を落とした。
なるほどつまり、ぶららは露出狂であり、見られることに興奮するらしい。
「昔は同性でも感じれたんだけど、今はもうだめ!異性じゃないと感じなくなった。異性に見られてると思うだけで涎が出てくるんだ。」
そう言って、どんどん足を広げる。
「でもね、自分からわざと見せるのはあんまり興奮しないんだ。戦闘中とかにスカートがめくれるとかそういう偶然見られる!ってのが最高に興奮するんだ。」
謎の性癖を暴露した。
「つまり、俺に偶然パンツを見られたいから、一緒に旅をしたいってことか?」
「その通りだよ!変態どうし仲良くやろうよー。」
したっと立ち上がってぶららは助態の手を握った。
「何かの拍子でボクの処女を奪ってもいいからさ。」
手をぶららのふとももに持っていく。
「その辺にしときな。」
もふともがぶららの首根っこを捕まえて助態から引きはがす。
「まぁ、助態さんは変態中の変態なんで、ぶららさんの願いはきっと叶うと思うっすけど、でもいいんすか?初体験が助態さんで。ウチも処女っすけど、助態さんはないっすわ。」
ぱいおが思いっきり失礼なことを言う。
「あら?そうかしら?私は初めてじゃないけど、助態みたいな人になら初めてを捧げてもよかったと思っているわ。」
「えーくびちさん趣味悪いっすよー。」
「あなたこそ、こんな顔のどこかいいの?」
ラーガの村のイケメンガチムチ門番の顔にくびちが変化しながら言う。
「あぁー。ウチを犯さないでー。だめっす。ウチまだ初めてだからダメっすー。」
そのままくびちはぱいおのでかい胸を揉みしだいた。
「このメス牛が!揉まれて感じているのか!」
「ダメっす。ウチ…汚されるっす。」
「…いいねこのパーティー!変態ばかり集まってるようだし!ボクも暫くお供させてほしいなぁー!」
改めてぶららが言う。
「ま、あなたが助態に見られたいだけの変態って分かったし、今のところ害はなさそうだからいいけど。何か変なそぶりを見せたら追い出すわよ?」
ぱいおに馬乗りになりなって胸を相変わらず揉みながらくびちが言う。
「私もそういうことなら文句はありません。けど、あまり変なことはしないで欲しいです。」
「私も純純さんの意見に賛成です。えっちぃのは嫌いです。そういうのが目的なら2人きりでやってください。」
純純とルブマも、ぶららがパーティーに参加することに、渋々ながら同意した。
「ウチは汚されてしまったので、ぶららさんが参加してもいいっすよ。」
完全に目がイッてるが、ぱいおも同意した。
助態はもふともを見た。
「…ま。アンタがいいならいいんじゃないの。」
ぷいっとそっぽを向きながらもふともは、ぽりぽりと頭を掻いた。
こうしてエロパーティーに、更なる変態が加わった。
「ロリコンにレズに腐女子に露出狂にむっつりのパーティーか。」
助態の呟きや吹き抜けた風が連れ去って、誰の耳にも届かなかった。
●
カローンの村を大きく迂回した一行は、相も変わらず賑やかだった。
カローンの村を過ぎた辺りから草原から平原に変わった。
「そういえば草原と平原ってどう違うんだろ?」
助態がふとした疑問を投げかける。
「ざっくりとだけど、平原は平らな野原を指す言葉で草は生えていなくてもいいのよ。草原は草が生えた野原で平らじゃなくてもいいのよ。さっきまで坂道とか多かったでしょ?」
くびちが謎のトリビアを披露した。
確かに、カローンの村を過ぎると道は平坦になっていた。
気のせいかもしれないが、草の量も少なくなっている気がする。
その分風がよく吹くようになった。
「うわー!風が強くてすぐにパンチラしそうだぁー!どうだい?助態。興奮はするかい?」
「いや、なんか物凄い変態がいると逆に萎えるというか何というか…」
「待ってくれよー。ボクを変態なんて罵らないでくれよ。興奮しちゃうじゃないか!」
ぶららが体をクネクネさせながら喜んでいる。
「どことなくアンタに似てるんじゃない?」
後ろでもふともがぱいおに言っている。
「はぁ?何言ってんすか。ウチあんな変態じゃないっすよ!それにウチは助態さんになじられても感じませんもん。ウチは顔を変化させたくびちさんになじられたいっす。何ならそのまま犯されたいっす!」
フンッ!鼻息を荒くしながらぱいおがもふともの言葉を否定した。
「んじゃあアタイは純純と色んなことをしようかねぇ。」
もふともはどうやらまた、純純とのあらぬ妄想で鼻血を出したようだ。
「色んなことって何ですか!私はもふともさんとはそういうことはしませんよ?」
「とはってことは純純さん、他の人とはするってことっすか?まぁーさぁーかぁー、助態さんとならそういうことをされてもいいとか思ってるんすか?」
「お!思ってません!」
バシリと純純が助態を叩いた。
「いつも叩かれて大変ですね。」
後ろで純純の隣にいたルブマが苦笑いする。
「それにしても…」
助態とぶららと一緒に先頭を歩いていたくびちが後ろを振り返る。
「かなり個性的なメンバーが集まったわねぇ。あんた達勇者とヒロインなのにかすんじゃうわね。」
にやりと助態にいたずらっぽく微笑む。
「いや、別に存在感がかすむのはいいんだけど?まぁ確かに個性的なメンバーではあるな。」
くびちに言われてそう返すと、平原の途中にポツンと洞窟があった。
「こんなところにポツンと洞窟…」
ボソリと助態が言う。
「噂によるとここには栗鼠族が住んでるって話しだよ。」
ぶららがにぱっと笑って言って更に続ける。
「ところでみんなはどうしてここに来たかったの?」
「あぁ。別に来たかったわけじゃないんだけどね。」
そう言ってもふともが簡単に経緯を説明した。
「カローンかぁー。潜入するために兎獣族を仲間に引き入れるわけねぇー。それなら栗鼠族は役に立たないんじゃない?工作が得意な種族でしょ確か。」
「いやだから別にアタイらも、リスの穴に用があるわけじゃないんだって。」
「あわよくば仲間に引き入れるつもりなの?」
キョトンとぶららが訊くが、言われてみれば助態も何しにここへ来たのかいまいち分かっていない。
ただ通り道にあるから寄ってみようか。みたいなノリだった気がする。
少なくとも仲間に引き入れようという魂胆はなかった。
「仲間に…するつもりあったっけ?」
助態が一応という感じでみんなに確認するが、誰もそのつもりはなかったことは、無言の返答で分かった。
「とりあえず兎獣族について聞くという目的でいいんじゃないかしら?」
みんな行き当たりばったりで行動していたため、何をするつもりだったのか誰も考えていなかった。
そんな中でくびちが提案した。
「そうですよね。とりあえず栗鼠族に聞いてみるということでどうでしょう?」
純純が引きつった笑顔で助態を見る。
助態も、そうだな!なんとかなるだろ!と言ってリスの穴に一行は入っていった。
●
リスの穴は普通の洞窟とは違っていた。
と言っても助態は生まれてこのかた洞窟という場所に行ったことがないので、普通の洞窟がどんなものかは分からない。
でも明らかにこれは違うだろうというのは分かる。
何しろリスの穴は、洞窟とは名ばかりの居住空間が広がっていたのだった。
助態達が入った洞窟の入り口が巨大な穴となっており、そこから縦横上下に小さ目の穴が空いている。
その穴が栗鼠族の通り道となっており、それぞれの穴の先にお店や各家族が住む家があった。
今、助態達は栗鼠族の一団に各穴の説明を熱心に受けていた。
栗鼠族曰く、自分達以外の種族がリスの穴にやって来るのは数十年ぶりらしい。
「ここがブッカケ一家が経営している食堂です。あそこがセーシー一家の家ですね。」
一生懸命案内してるのは、ハクダク・スキというメスの栗鼠族だった。
みんなの名前が個性的すぎると助態が思ったのは言うまでもない。
「とりあえず皆さんのことは食堂でお話を聞かせてください。あと勇者様はぜひ私にその股間から出る白い液体を我々に分けてくれませんか?」
ハクダクが助態を見上げながら言う。まるで上目遣いだ。
「はぁ?」
驚く助態を他のメンバーが見つめる。
「…別にいいんじゃないかい?減るもんじゃないし。」
もふともだ。
「そうっすね。性獣の助態さんもこれで一発抜ければスッキリするんじゃないっすか?」
とぱいお。
「いっ一発?抜く?スッキリ?えっちぃのはダメって言ったばかりじゃないですか!」
周りをキョロキョロしながらルブマが叫ぶ。
「え?変な話なんですか?」
「純純は本当に純粋なんだなー。助態が1人でシてるところを偶然ボクが目撃したらどうなるかなぁ?物語みたいに代わりにお前のも見せろとか言われるかなぁ?」
ぶららは涎を垂らしている。
「よ!涎を私の服で拭かないでください!」
その涎を純純の服で拭こうとして怒られている。
「聞いていますよ?殿方は1人でするときに、ホールと呼ばれる道具を使うと。我々栗鼠族は工作が得意な種族です。この本気のホールを試してください!極上の快楽を勇者様に与えますよ!」
ハクダクがはぁはぁしながら助態に迫る。
何やら大人の玩具みたいのを手に持っている。
「じゃ、私が手伝ってあげるわ。」
と言って悪ノリするのはくびちだ。
「待って待って!本気のホールは気になるけど、それ以前になんで俺のが欲しいの?」
股間に大人の玩具を当てられそうになりながら助態が聞く。
「え?普通に美味しいじゃないですか?」
キョトンとハクダクが言う。
「おいしいかしら?あれ、目に入ると染みるし、匂いがいつまでも残ってるし髪の毛がキシキシになって最悪なのよね。」
くびちが謎の経験を語っている。
どうやらくびちはかなり経験豊富なようだ。
「実はこのパーティーで一番の変態ってくびちさんなんじゃないっすかね?」
ひそひそルブマに言うぱいおの声がくびちに聞こえたらしい。
「何ですって!」
そう言いながら、イケメンガチムチ門番の顔に変化したくびちが、いつも通りぱいおに馬乗りになって胸を揉みしだいている。
「あぅぅぅー♡もうウチはだめっす。ルブマさん。あとは任せたっす。」
「な!何で私なんですか!」
「そりゃあルブマが実はエロいからじゃん?」
慌てるルブマにもふともが正直な意見を述べる。
「えっ…えっちじゃありません!」
つっかえながら言ってる時点で説得力はなかった。
そうこうてんやわんやしている内に、一行はブッカケ一家が経営しているという食堂の席に着いた。
ハクダクが適当に料理を持ってくると言うので、そのまま任せることにした。
「それにしても助態さん。いいんすか?」
にやにやしながらぱいおが言う。
「何がだ?」
「男って1日でも抜かないと大変だって言うじゃないっすか。見たところ助態さんウチと知り合ってから1回も抜いてないっすよね?発情期の助態さんが長い間抜いてないってかなりヤバいんじゃないっすか?しかも毎度毎度くびちさんの胸まで揉んでて。助態さんのキングコブラも暴発寸前なんじゃないっすか?」
「勝手に俺のち●こに名前をつけるな!俺のはエクスカリハーだ!」
ここで助態は一度純純に殴られた。
「確かにこっちに来てから一度も抜いてないし、ルブマの恰好はショーパンにニーハイでモロにロリ属性だし、村や町に滞在している時のぱいおはジャージ姿だから胸が常に揺れてるし、もふともは服装が変態だしくびちの胸は最高に柔らかいし、ぶららは存在がエロだし、本当ヤバいよ。」
「なら、栗鼠族の道具とやらで抜いてもらったらどうかしら?私が手伝ってあげるわよ?とゆーか、そんなに抜きたいならいつでも私の体使っていいのよ?なんなら本番してもいいのよ?」
長い真っ赤な髪の毛をセクシーに後ろに掻き上げながらくびちが言う。
「え?いいの?じゃあぜひ今夜!」
助態が身を乗り出すとルブマが突然激怒した。
「ダメに決まってるじゃないですか!」
「何でアンタが怒ってるんだい?」
キョトンとした顔でもふともがルブマに言う。
そう言うもふとももイスから立ち上がっていた。
2人を見たくびちがにやりと意地悪くほくそ笑む。
「いいじゃないねぇ?私も助態とシたい。助態も私とシたい。何か問題がおありで?」
「問題おおありだよ!ボクが助態に初めてを捧げるんだから!くびちはボクの後だよ!」
ぶららがずいっと前に進み出て、くびちの提案を拒否した。
「確かに俺も今夜一度に2人の相手をするのは大変かなぁ?いやでも体力的にまだイケる気がするぞ。」
拳を作りながら助態が言うも、純純の言葉にかき消されてしまった。
「もう!皆さんまじめに話をしてください!」
●
ハクダクが料理を運んできてくれた。
別の種族かと思いきや、食べているものは人間と同じもののようだ。
茹でポテト、ピザ、パスタ、焼き魚、ジャム、パン、白米、シチュー、肉の香草焼きを各自取り皿に取り分けた。
「さてそれでは詳しい話をお伺いしてもよろしいですか?」
さっきとは打って変わって真面目な言い方でハクダクが聞く。
「なぜ栗鼠族ではないあなた方人間が、我々リスの穴に?もしも栗鼠族を滅ぼすためにやって来たのだとしたら、私もそれ相応の対応を取らざるを得ません。」
シュッと拳を握ってパンチの構えを取る。
「いやいやいや。待って待って待って。滅ぼすとかそういうのはないから!」
慌てて助態が止めて、簡単ないきさつを説明した。
「…兎獣族にモンスターに滅ぼされた村カローンですか…」
話を聞き終えたハクダクが、先ほどは失礼しました。と頭を下げた後に言う。
「残念ながら我々は他の種族のことを知りません。ただ、兎獣族は寒い土地にいると聞いたことがあります。」
「寒いところ?パッとしない情報だねぇ。」
焼き魚を食べながらもふともが言う。
「申し訳ありません。我々もこの穴の中でしか生活していないもので。」
穴と言いながらハクダクが自分の尻を指さしている。
「えっちぃことはしないでください!」
ルブマが怒る。
「ルブマちゃんの穴を使って欲しかったんですか?」
ハクダクが見当違いなことを言いながら小首を傾げる。
どうやら、真面目な話にはなりそうもなかった。
「イクあてがないなら、この先に人間の町があると聞いたことがあります。」
しっかりとハクダクが情報を教えてくれる。
「よかったら案内しましょうか?」
しかも親切にも案内までしてくれるらしい。
「じゃあボクもそこまで一緒に行こうかな。」
どうやらぶららも行ったことない町まで同行するようだ。
●
「なんれすか?これはぁ?助態さんの秘剣ですかぁ?」
ベロベロに酔っぱらったルブマが助態の股間を触ろうとしていた。
それを見てにやけながらもふともが言う。
「相変わらず酔うとエロくなるねぇー。」
これから先のことが決まったことで、全員で急遽宴会になったのだ。
「お酒一滴で酔うなんてだらしないわよ?」
くびちはもう5杯目だ。
「ボクの助態だよー?ルブマは1人でシてればいいじゃーん!」
ぶららがルブマの手を払いのける。
「もう1人でするのは飽きました!寂しいんですよぉー1人は。助態さんの秘剣で私を満足させてくださいよぉー。助態さぁーん。」
酔った勢いでルブマが助態にキスをする。
「あっ!ルブマさん飲みすぎですよ!」
純純が怒ってルブマを引きはがす。
ぱいおはふざけて、このきぃー!この泥棒猫!とか言っている。
「ふへへぇー。私の初めてのキス…助態さんに奪われました♡」
「寝ちゃいましたねー。正直、助態さんのどこがいいのかウチにはさっぱりっすね。」
ルブマを純純と一緒に抱きかかえながらぱいおが言う。
「ま、やるときゃやる男だけどアタイはやっぱ純純一筋だなぁー。」
運ばれるルブマを見ながらもふともが言う。
手には純純の純白パンツが握られていた。
「何を持っているの?」
くびちがジト目で訊く。
「純純のパンティ♡アタイのスキル、盗みでさっきかすめ取ったの!」
くんくん匂いを嗅いでいる姿を見てさすがのぶららも引いていた。
「もふとも…ど変態だぁ。」
「あ!アンタに言われたくないよ!助態に見られるためだけに生きているこの露出狂が!」
「いやぁー?変態はボクにとっては褒め言葉だよー。」
「皆さんは勇者様のことがお好きなんですね。」
にこりと笑ってハクダクが言う。
ちょこんと助態の膝の上に座っている姿が何とも可愛らしい。
「私は大好きよ。」
くびちは肯定したがもふともは否定した。
「アタイは別に。」
「でももふとも顔赤くなってるよ?」
ぶららがキョトンとしながら言う。
「なっ!なってなぁーい!」
くびち、もふとも、ぶららのやり取りをテーブル越しに眺めながら、助態がハクダクに訊く。
「さっき言ってた町ってここからどのくらいのところにあるの?」
「そうですね。歩いて1週間といったところでしょうか。ただ、私も行ったことはないので詳しくは知りませんよ?」
それでも十分だと助態は思った。
●
月の無い夜――
いつもなら風が強く吹くのに珍しく吹いていない。
酔いを醒まそうと助態は洞窟の外に出ていた。
助態が外に出るのを見かけたぱいおは、もふともを誘ってこっそり後をつけることにした。
「きっと一人でスるんすよ!この際どんな感じでするか覗いておきましょ!」
ウキウキしながらぱいおが言う。
「何でだよ。別に助態が1人でスるのに興味なんてないよ?」
「いやー、この際だから3人で別々にシてみんなスッキリしちゃいましょうよ!」
てへへとぱいおが笑う。
要はぱいおは溜まってるわけだ。
「だったら1人でスればいいだろ?何でアタイを誘うのさぁー?こんないつ誰が来るかも分からない場所なんて集中できないじゃないか。」
「えー?連れオナって一回してみたかったんすけどだめっすか?」
ぱいおが岩陰に潜んで自分の巨乳を揉み始めた。
「あ、ウチに百合属性はないっすからね?」
念のためにとぱいおが忠告する。
「わ!分かってるよ。よく人に見られながらできるね。」
「こんなのお風呂と一緒っすよ。ってあれ!」
今しがた洞窟から出てきたルブマを指さしてぱいおが言う。
「何でルブマが?あいつも一人で?ってんなわけないよな?」
もふともの言葉を聞きながらぱいおは自分の胸を揉む手を止めた。
「まさかルブマさん…助態さんに告白するつもりっすかね?」
「はぁ?」
思わず大きな声を出してしまったもふともの口をぱいおが塞ぐ。
「しー!声がでかいっすよ!あ、欲情しないでくださいよ?」
そう言ってぱいおがもふともから離れる。
もふともとぱいおはこっそり岩陰に身を潜ませながら、助態とルブマの様子を見ることにした。
『はぁー。空気がきれいだなー。あっちの世界じゃ感じれなかったことだなぁー。』
ぼふっと助態は仰向けに倒れた。
『月も無くて街灯もないと星の灯かりが明るく見えるって本当なんだなー。』
「風邪…引きますよ。」
ルブマの声がする。
助態は上半身だけ起こして座ったまま振り返った。
「ルブマ…どうしたんだ?」
「その…さっきのことを謝ろうと思って…」
そう言ったルブマの声は小さすぎて、至近距離に居ない助態には聞こえなかった。
「え?」
「隣…いいですか?」
遠慮がちにさっきよりもしっかりとした声でルブマが訊く。
ドキン。
助態の心臓が跳ね、やや緊張気味にあぁ。と返事をした。
思い返せば助態は、ここ最近恋なんてしてなかった。
体だけの簡単な関係の方が楽だと考え、恋の駆け引きはもちろん恋愛がどんなものかも暫く忘れていた。
それこそ、胸がドキドキする感覚なんて何年ぶりのことだった。
ちょこんとルブマが隣に座る。
いつもと同じ探検隊のような短いショートパンツにニーハイを履いている。
「そんな恰好で寒くないの?」
「これでも女子ですから!」
ない胸をドンと叩く。
とはいえ季節は冬に向かっている。しかも夜だ。
「これ。」
と言って羽織っていた薄めの上着をルブマの足にかけた。
「はぇぇー。助態さんって意外と紳士なんすねぇー。」
ひそひそとぱいおがやや興奮気味にもふともに言う。
「あぁ。たまにそういうところがあるかもね。…しっ!」
助態が話し出したので、口に人差し指を当ててもふともがぱいおを黙らせる。
「で、何しに来たの?」
「その…先ほどはすみませんでした…まさか飲み物にお酒が混ざっているとは思いませんでした…」
「ん?あぁいいって。このパーティーやってりゃ多少のエロは別に気にならなくなるもんさ。」
「え、えっちぃことではありません!そ、それもありますけど…その…きききききキス…してしまいました…」
顔を赤らめてルブマが言う。
しかし助態の反応はルブマが予想したそれとは全く違っていた。
「あぁそんなことか。別にキスくらいどうってことないよ。」
「どうってことないなんてことはありません!」
すくっと立ってルブマが怒る!
ハラリと助態から借りた上着が地面に落ちる。
「助態さんにとってはどうでもいいことなのかもしれませんけど、私にとってはどうでもいいことじゃないんです!」
ポロリと涙がルブマの頬を伝う。
「は…初めてだったんですよ?助態さんにとってはその他大勢の1人かもしれませんけど、私にとっては初めての人になるんです!」
「いや俺もそんなつもりで言ったわけじゃないんだけど――」
「いつもいつもえっちぃことばっかりしてるからですよ!乙女心が分かっていませんね!」
助態の言葉を遮ってルブマが言う。
片手で涙を拭って笑顔を見せる。
負け惜しみの強がりの笑顔だ。
「私の初めてを奪った責任は重いですからね!」
くるりと後ろを向く。
動きに合わせて短い茶色い髪がルブマの顔を追う。更に拭きそびれた涙がそれに追随する。
そのままたたたっと洞窟の入り口まで駆けていく。
両手を後ろに組み、ぴょんっと助態の方に振り向く。
「絶対に振り向かせてみせますからね!」
べーっと舌を突き出してルブマは洞窟の中に駆け込んでしまった。
呆然と立ち尽くす助態を見て、もふともとぱいおもそっと洞窟へ帰って行った。
「見てはいけないものを見てしまった気がするっす。」
「そうだねぇー。アンタは助態のこと何とも思ってないんだろう?」
「?そうっすね。今のところ胸キュンエピソード0っす。」
うーんと、助態とのことを思い出しながらぱいおがもふともに答える。
「ルブマがライバルかよ…」
ボソリと呟いた呟きは、ぱいおには聞こえなかった。
「え?何すか?」
はたまた聞こえないフリをしているだけなのか――
先ほどまで止んでいた風がもふともの呟きを連れ去って洞窟の外へと運んで行った。