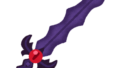「ったくお荷物だなー」
文句を言いつつ助態を背負っているのはもふともだ。
「だからウチが運ぶっすよ? ウチが見捨てて先に逃げたのが原因なんで」
「私が助態さんを運びます」
ぱいおがもふともから助態を引き取ろうと進み出ると、それをルブマが遮った。
「あん? アンタじゃ無理だろ」
明らかにパワータイプではないルブマの申し出をもふともは断り、ついでにぱいのも断った。
何だかんだ文句を言いつつも、自分が運びたいのだ。
「にしても、大した時間1人で過ごしてたわけでもないのに、ここまで気絶するもんかねぇ」
はあはあがペシペシと助態の頬を叩く。
「モンスターの巣のど真ん中に居たんだ。気もかなり張っていただろうよ」
ティーパンが助態を庇うと、隣でちあも頷く。
「助態は最弱じゃからのぅ」
「最弱の勇者ねぇー」
ちあの言葉を聞いてもっこりがケタケタ笑うが、決してバカにした感じの笑い方ではない。むしろ不思議そうな笑い方だ。
「それが勇者の魅力なんだよ」
私には全く分からないけど。と付け足しながらティーパンが締めくくる。
メンバーはゆっくりと、先へ進んで行った。
●
パチリ。
火が爆ぜる音が心地いい。
ずっとこのまま夢心地で居たい。
そんなことを考えながら、助態は先ほどまで起こったことを脳内再生していた。
……黄虎とザギと戦って逃げ出して、みんなと再会して……
「ふげら!」
謎の言葉を発しながら助態は勢い良く起き上がった。
キョロキョロと辺りを見渡して、今の状況を理解する。
「俺、気絶してそれから……」
「アタイがおぶってやってたんだよ」
焚火に木をくべながらもふともが見向きもせずに言う。
「お、おぅ……」
ありがとう。と言おうとしなのに、素直に言葉が出なかった。
「まだ横になってな。小休止をしたら出発する。その時には勇者の判断が必要になるからさ」
そう言ってティーパンが指さす。
その先には、真っ直ぐ進む道と左右に別れる道があった。
『なるほど。俺が起きるまで休憩してたってわけか……』
自分が不甲斐ないと思いながら、再度助態は横になる。
瞬間、さっきまでは気付かなかったが誰かの顔が目の前にあった。
「うおっ!」
「うっさいね。横になっとけって言われただろ?」
めんどくさそうにもふともが言うが、助態はそれどころじゃない。
だって、あのぱいおが助態と添い寝をしていたのだから。
「いやでもさ……」
そこまで言って助態は、もう1つのことに気づく。
なんともふともが膝枕をしてくれていたのだ。
「???」
もう何が何だか分からなかった。
「さっさと横になるといい。それとも無理やり横にさせようか?」
笑いながらティーパンが言うが、目の奥が笑ってない。
言葉もなく、助態はもふともの膝の上に再び頭を乗せた。
「意外と硬いな」
ボソリと言うがもふともにはちゃんと聞こえていた。
「はっ倒すよ?」
思いっきり殴られた。
●
「まさか雷獄の洞窟が迷路になっているとは」
何度目かの分かれ道にうんざりしたように、もっこりが言う。
「これって、俺たちをここから出さないためにわざとこうなってるとかないよね?」
念のために助態が聞くが、そんなことはあるはずもないかった。
洞窟の形を変えるなんてありえないことだ。
ましてや、雷でできている洞窟だ。
そう簡単に形が変えられるわけがない。
それでもこう何度も分かれ道に遭遇し、何度もモンスターと戦闘をすると嫌でもそんなことを考えてしまう。
既にみんなの精神力も疲弊しきっている。
「ここらで休憩しますか?」
何度目かの提案だ。
「いや、まだ行けるところまで行こう。まだ魔力は残ってるから次の戦闘があっても平気だ」
休めば休むほど神経が磨り減ることをティーパンは知っている。
できるだけ休まずにこの迷路を抜けたいのだ。
それでも……
「ティーパン、さすがに休憩をとる必要があると思うんじゃが?」
珍しくちあが音を上げる。
「さすがの幼き天才も人の子か」
そうは言ったが、実際ティーパンも限界だった。
そして休んだら全員の進むスピードも上がった。
「やっぱり休むと効率が上がるねー」
目の前の雷スライムの攻撃を避けながらティーパンが言う。
今、ようやく雷獄の洞窟の出口らしい場所にたどり着いていた。
そして雷スライム1匹と遭遇していた。
明らかに周囲の雷がなくなっている部分があるので、間違いなく出口だろう。
この雷スライムさえ倒せば雷獄の洞窟から抜け出せるわけだ。
『長かったな……』
助態は、そもそも魔界へ来ることになったきっかけを思い出しながら、何か感慨深いものがこみ上げてくるのを感じた。
王の口が生み出したであろう吸収スライムを倒すために、箱の庭園を目指していた。
そこで船の墓場を迂回するために、ロンラーとかいう怪しい村で騙されて死の国へと誘われてしまった。
死の国でデスキングに掘られて、魔界で鬼痴女三姉妹と出会い、魔界を抜けるために幽霊城へ向かい雷獄の洞窟へとやって来たわけだ。
考えれば考えるほど長い道のりだった。
「ふおぉぉぉぉー!」
ぱいおが大きい盾を構えて雷攻撃を防いでいる。
『嘘だろ?』
通常盾は金属製である。
雷を通してしまうため、雷や熱関連の攻撃を防ぐのは困難のはずだ。
しかしぱいおはそれを防いでいた。
「ビリビリ効くっすぅー」
いや。防いでいるわけではなかった。ただ感じているだけだった。もちろん命の危険がないわけではない。
「バカ! 感じてないでさっさと避けろ!」
助態の声にぱいおがムッとする。
「ウチの至福の時間を奪わないで欲しいっす」
『あいつどんどんMになってないか?』
困惑する助態をよそに、ティーパンとちあが雷スライムをあっさりと倒してしまった。
「危険度Aのモンスターも1匹なら余裕なのか……凄いな金色の戦士と幼き天才は……」
驚くヌルヌルの隣で、純純は助態とぱいおのやり取りを見てモヤモヤする自分に戸惑っていた。
そんな純純の様子に気づかないまま、メンバーは暗闇の森へと足を踏み入れたのだった。