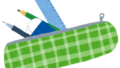「ちあっ!」
カーテンを開けて目の前に飛び込んだ光景に助態は叫んでいた。
ちあが裸で両手両足を拘束され、人間の男に今にも襲われようとしていたのだ。
「あれだけのカーテンのトラップを抜けてきたのか……」
扉の絵とかはこの男が言うにはトラップだったようだ。
「君たちは下がってな。ちあを見るんじゃないよ」
ティーパンが助態、ヌルヌル、もっこりに言い、双頭蛇を召喚した。
「誰かちあに服を貸してあげな」
そう言い置いてやや距離があるちあのところまで一瞬で間を詰めた。
「なっ! 僕と戦うつもりか?」
小さなナイフを持ってティーパンに立ち向かおうとするが、ティーパンは双頭蛇を従え大刀も掲げている。
「ティーパンさん……キレてるな……」
助態の呟き通り目の前で仲間が襲われそうなのを見て、ティーパンは完全にキレていた。
何よりもティーパンは女の味方という感じの人物なのだ。
「戦う?もう終わってるだろ?」
蛇で男を締め上げ、大刀で首を飛ばすと、人間の姿からみるみるうちに別の姿へと変身した。
小さな丸っこい体にコウモリの羽を生やし、ニワトリのような足が付いていた。
「こいつはこんろりだ」
はあはあが目の前の倒されたモンスターを見て言う。
「私の妹たちを知ってるだろう?」
ちんちんやぱいぱい、まんまんのことだ。
血は繋がっていないが妹だと言う。
「あの娘たちもね、こいつらに襲われたことがあってね。そのせいでそのなんだ。性に興味津々なんだよ」
「何もされてないかい?」
ちあの拘束を解いて毛布にくるませながらティーパンが問う。
「平気じゃ。ギリギリのところじゃったがちあの貞操は守られたのじゃ」
ニヤッとちあが助態に微笑みかける。
ちゃんと抱っこしてあげなさい。とティーパンにちあを渡され、助態は戸惑いながらもちあを抱っこした。
何もされていなくて安心した自分がいることに、助態は気づかなかった。
●
助態たちはカーテンの間に再び戻ってきた。
まだまだカーテンはたくさんあり、先ほどの変な音も相変わらずしている。
「どうする? みんな揃ってるけどまだカーテンを開け続ける?」
ティーパンが助態に問う。
「こんろりとかいうモンスターがカーテンはトラップって言ってましたよね?」
助態がそう言うとティーパンが頷く。
「それならわざわざ開ける必要はないかと思います。それよりも先に進みませんか?」
「私は勇者の意見を支持するよ?」
助態の提案をティーパンは基本反対しない。
他のメンバーも実力者のティーパンが賛成するならそれを疑わない。
こうしてメンバーはカーテンの間をさっさと抜けることにしたのだった。
一本道を進めば進むほど、怪しい音に近づいているのに助態は気が付いた。
「のぅ助態。くりすますって何なのじゃ?」
ちあがこんろりから聞いた聞きなれないワードを助態に訊く。
「あぁ。俺がいた世界にもあったなそういうイベント。大人から子供までワクワクすいるイベントでさ、一部の人以外みんなが大好きなんだ。サンタクロースってゆー人が子供にプレゼントを届けてくれるだとか、恋人同士でプレゼントを交換するだとか、恋人の季節だとかそーゆーとにかくほとんどの人みんなに好かれるイベントなんだよ」
助態が懐かしそうに話すが、どうやらこの世界の人たちにはピンとこないようだ。
「なんでそんなイベントがみんな好きなんじゃ?」
「あぁ。子供たちはお菓子とかおもちゃを欲しがるもんだからな。大人はやっぱりロマンチックだからじゃないか? 何でって改めて聞かれると難しいもんだな」
ふむ。と考えながら助態が答えると、目の前に再び大きな扉が現れた。
開ける以外の選択肢がないため、メンバーは扉を開けて先に進んだ。
●
扉を開けた瞬間、強烈な光にメンバーは目がくらんだ。
さっきまで暗い部屋だったのに急に明るい部屋になったのもある。
ガシャンガシャンやかましい音が鳴り響く部屋だ。
先ほどからしていた謎の金属音もこの部屋から聞こえていたことが分かる。
助態には、なんかの工場のように見える。
「何だいこのやかましい部屋は」
もふともが両耳を塞ぐ。
「金属同士が勝手に動いているのは魔法かしら?」
ロボットや機械という概念がないのか、くびちが勝手に動く機械を見て不思議そうにする。
「術者が近くにおらんのにオートで物を動かすことはまず不可能じゃ」
その隣でちあが真面目な顔をしている。
さすがは幼き天才だ。
「遥か遠い国には、金属ではないが木製の人形が自動で動く技術があると聞いたことがある。確かカラクリとかいう名前だったかな」
「あ、ウチもそれ聞いたことあるっす。物を運んだりするらしいっすよ」
ティーパンの言葉にぱいおが反応する。
時折ぱいおは博識なところがある。
「これは機械だよ。ぱいおやティーパンさんが言ってるカラクリとはまた違った技術で多分どこかに電源があると思うんだ」
助態が自分が生きていた世界の知識を教えると、ちあが電源? と問うてきた。
「あぁ。まぁ簡単に言えば電気で動いているんだ。電気ってのは雷をもっと弱くして人間が扱いやすくしたようなものだ。人工的にその電気を発生させられるんだけど、俺は専門家じゃないからその辺はよく分からない」
助態が頷きながら言うと、雷を自在にという言葉にみんなが驚いた。
「まぁそういう技術がここにもあるってことだな」
「それがモンスターの間だけで共有されているとしたら、人間に対してかなりの脅威になるぞ……」
助態の楽観的な言葉にティーパンがおののく。
「いや、電気がなければ動かないしガソリンとかそーゆーのはないだろうから、そこまで脅威じゃないと思いますよ」
戦闘中には使えないだろうと助態は言う。
戦争のようにガソリンなどを使って戦闘機などを飛ばすなら分からないが、電源を使わないと動けない機械など、戦闘中に使えるわけがない。ましてやここは魔法がある世界だ。
機械よりも魔法を扱う方が合理的である。
「なんか助態さんが少しかっこよく見えてきたっす!」
ぱいおが目をパチクリさせる。
「なんでそんな表情なんだよ!」
やや嫌そうな顔をしたぱいおに助態が突っ込む。
「それで、ここは何をする部屋だと勇者は見る?」
ティーパンが機械を唯一知っていた助態に問う。
とは言われても助態は機械に詳しいわけではない。
見たところ、何かの部品を作っているように思える。
それが何の部品かは分からないが、金属を切り出し、加工し、研磨して金属は丸い手のひらサイズになってベルトコンベアで運ばれていた。
そこからプレスされて薄くされていた。
「円月状の刃物のような武器を作ってるように見えますけど何とも言えないです……」
助態が言うように、完成品が薄い円状の物なだけで、それを何に使うのかはさっぱり分からなかった。
「ただ、この機械を動かしている電気がどこから来ているのかは気になりますね……」
電気で動いている以上、発電している施設や場所があるはずだと助態は言う。
「それに、誰が何の目的でこの金属を使うのかも気になるっすよね」
珍しくぱいおもまじめだ。
ぱいおがまじめな時はいつも、それだけ切羽詰まった状態であることが多い。
「そのでんきとかゆーやつは自動で出るとかはないのか? 雷は自然現象だろ?」
電気そのものが理解できていないもっこりは、電気も雷同様に自然に発生すると思っているようだ。
「その電気を発生させるための装置があるはずなんだ。通常はそれを線に通してってそんなことはどうでもいいか。とにかく、その発生させた電気が送られることで機械は動くんだ。だから、この機械を動かしている電気がどこから来ているのかが分かれば、この機械が何に使われているのかも分かるかもしれない」
助態の予想は、一般的な世界では正しい。
しかしここは異世界。
助態の予測はその一般的を上回っていたのだった――