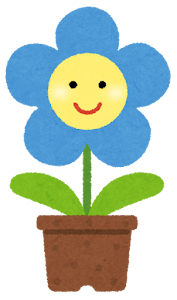スズランは、決めていた。
逃げられている理由が分からなくてもいい。
答えが怖くてもいい。
――それでも、確かめる。
放課後。
人の少ない昇降口で、彼女はアスターを待っていた。
靴箱の前に現れた彼は、スズランの姿を見た瞬間、はっきりと足を止めた。
その反応だけで、胸が締めつけられる。
「……スズラン」
名前を呼ばれる。
でも、距離は詰めてこない。
いつものことだ。
「少し、話せる?」
声が震えないように、意識して言った。
「今は――」
「大丈夫。すぐ終わるから」
断られる前に、言葉を重ねる。
アスターは、ほんの数秒迷ってから、うなずいた。
校舎裏。
夕方の風が、少し冷たい。
沈黙が、先に限界を迎えたのはスズランだった。
「私、何かした?」
単刀直入だった。
「……違う」
即答。でも、歯切れが悪い。
「じゃあ、嫌われた?」
「それも違う」
否定は、速い。
だからこそ、次が出てこない。
スズランは、ぎゅっと指先を握った。
「だったら……どうして、避けるの?」
アスターは、答えない。
目を伏せ、言葉を探している。
――いや、探していない。
言えない。
その事実が、はっきり伝わってきた。
「ねえ」
一歩、近づく。
反射的に、アスターの肩が強張った。
その瞬間、確信する。
――やっぱり。
これは、私の問題だ。
「理由、教えてくれなくていい」
自分でも驚くほど、落ち着いた声が出た。
「でも、逃げられるのは……嫌」
視線が、ぶつかる。
アスターの目は、怯えていた。
怒りでも、嫌悪でもない。
恐怖だ。
それが、何より怖かった。
「……近づかない方がいい」
ようやく、絞り出された言葉。
スズランは、首を振る。
「それ、理由になってない」
「……危ないんだ」
声が、わずかに震えた。
「私が?」
「……俺が」
一瞬の沈黙。
その答えは、スズランの中で、別の意味に変換された。
――この人は、自分を責めている。
「だったら」
もう一歩、近づく。
今度は、アスターは下がらなかった。
「一人で抱えないで」
その言葉に、彼の表情が歪む。
拒絶されると思った。
突き放される覚悟も、していた。
でも。
アスターは、何も言えなくなった。
スズランは、その沈黙を選ぶ。
「私は、理由を知らない」
はっきりと、宣言する。
「でも、それでもいい」
風が吹き、髪が揺れる。
「近くにいることで、何か起きるなら」
一瞬、躊躇ってから。
「……それも、私が選ぶ」
アスターの視界が、揺れた。
――見えてしまう。
スズランの周囲に、
淡い光が、確かに強まっていく。
進行度が、上がる。
原因は、分かっている。
彼女が、自分の意思で踏み込んだからだ。
「やめろ……」
懇願に近い声。
「お願いだ」
スズランは、困ったように笑った。
「ごめんね」
その謝罪は、拒絶ではなかった。
「でも、逃げられる方が、もっと怖い」
夕暮れの中で、
二人の距離は、もう逃げ場のないところまで縮まっていた。
スズランは、理由を知らない。
世界の仕組みも、フラグの意味も。
それでも。
彼女は、自分で選んだ。
その事実だけが、
残酷なほど、はっきりしていた。