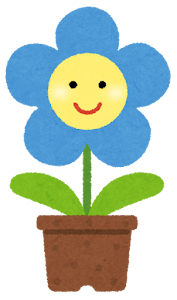放課後の教室は、昼とは別の顔をしている。
机の影が長く伸び、窓の外はオレンジ色に染まっていた。
部活に行く生徒の足音が、廊下の向こうで遠ざかっていく。
アスターは、いつものように席に残っていた。
ノートを開いている。
鉛筆を走らせ、書いては止まり、また書く。
集中している――ように見えて、
その実、周囲を強く拒絶しているようにも見えた。
「……アスター」
その声に、彼はびくりと肩を揺らした。
顔を上げると、スズランが立っていた。
鞄を持ったまま、帰るでもなく、立ち去るでもなく。
「なに?」
短い返事。
それだけで、少し警戒しているのが分かる。
スズランは、彼の机の横に立った。
「もう帰らないの?」
「……あと少し」
視線はノートから外れない。
スズランは、あえてそのノートを見ないようにした。
視線を合わせるのは、アスターの顔だけ。
「ねえ」
「なに」
会話が、やけに淡白だった。
スズランは、一度言葉を飲み込む。
そして、できるだけ何気ない調子で言った。
「最近、疲れてない?」
アスターの手が、止まった。
「……別に」
「そっか」
スズランは小さく笑う。
「でもさ、授業中も放課後も、ずっとそれ書いてるじゃん」
アスターは、ようやくノートから目を離した。
「……気になる?」
問い返しは、少しだけ棘を含んでいた。
「うん」
スズランは、否定しなかった。
「だってさ。前は、そんなタイプじゃなかったでしょ」
それは、事実だった。
クラス最底辺。
目立たず、話さず、ただ流されるように過ごしていた少年。
それが今は、
“何かに追われるみたいに”書き続けている。
アスターは、視線を逸らした。
「……変わることもあるよ」
「理由は?」
間髪入れずの質問。
アスターは、一瞬だけ言葉に詰まった。
「……必要だから」
「必要?」
スズランは、その言葉を繰り返す。
「なにに?」
沈黙。
教室の時計の音だけが、やけに大きく響く。
アスターは、ノートを閉じた。
その仕草が、どこか“守る”みたいで、スズランの胸がざわつく。
「……誰かに、言うつもり?」
ぽつりとした声。
それは質問であり、警告にも聞こえた。
スズランは、首を振った。
「言わないよ」
即答だった。
「ただ……心配なだけ」
アスターは、彼女を見る。
その目には、疑いと戸惑いと、ほんの少しの安堵が混ざっていた。
「……変なこと、考えてない?」
スズランは、静かに踏み込む。
「たとえばさ。
自分だけが何かを背負わなきゃいけない、とか」
アスターの表情が、わずかに強張った。
「……どうして、そう思う?」
「なんとなく」
また、その言葉。
でも今度は、嘘じゃなかった。
「アスターってさ」
スズランは、声を落とす。
「優しいよね。
だから、怖いんだよ」
「……怖い?」
「うん」
スズランは、彼の目を見つめた。
「その優しさがさ。
自分を壊す方向に行ってる気がして」
沈黙。
アスターは、何も言わない。
否定もしない。
肯定もしない。
それが、何よりの答えだった。
スズランは、胸が少しだけ苦しくなる。
「ねえ、アスター」
最後の一歩。
これ以上は踏み込まないと決めた、ぎりぎりの線。
「それ……危ないことじゃないよね?」
彼は、しばらく黙っていた。
そして、ようやく口を開く。
「……誰かが、傷つくことはある」
静かな声だった。
まるで、事実を述べるだけのように。
スズランの背中を、冷たいものが走る。
「でも」
アスターは続けた。
「……それ以上に、助かる人もいる」
スズランは、言葉を失った。
(……やっぱり)
確信が、恐怖に変わる。
これはただのノートじゃない。
これは――選別だ。
「……ねえ」
スズランは、最後に言った。
「それ、ちゃんと一人で決めてる?」
アスターの脳裏に、ダリアの顔が浮かぶ。
答えは、出なかった。
「……ごめん」
それだけ言って、彼は視線を落とした。
スズランは、それ以上何も聞かなかった。
「……分かった」
そう言って、背を向ける。
教室を出る直前、彼女は振り返った。
「無理しないで」
その言葉は、祈りだった。
扉が閉まる。
残されたアスターは、閉じたノートに手を置く。
そして、心の中で呟いた。
(……もう、無理なんだ)
遠回しな質問は終わった。
次は、もっと直接的な“選択”が迫ってくる。