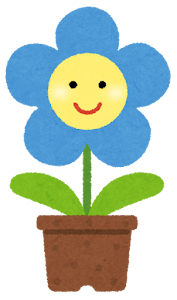放課後の職員室は、昼間よりも静かだった。
コピー機の音。
キーボードを叩く音。
蛍光灯の微かな唸り。
その中で、ミモザはファイルを閉じ、ため息をひとつ落とした。
「……やっぱり、気になるわね」
独り言のように呟く。
机の上には、数枚のプリント。
事故報告書。
生徒からの聞き取りメモ。
そして――匿名の投書。
『あの子は知っていたと思う』
『事故の前に、ヒヤシンスくんを見ていた』
『何も言わなかったのが、気持ち悪い』
どれも、決定的な証拠にはならない。
ただの不安と憶測の集積だ。
けれど。
教師という立場は、
「何も起きていないから放置する」ことを許してくれない。
「……予防、か」
その言葉を、心の中で繰り返す。
予防。
問題が起きる前に、芽を摘むこと。
教育現場では、正義の言葉として使われる。
だが同時に――
最も人を追い詰めやすい言葉でもある。
ミモザは、ふと職員室の奥を見る。
そこに座っているのは、学年主任のアイリスだった。
厳格で、規律を重んじる教師。
生徒からは少し怖がられているが、管理能力は高い。
ミモザは、椅子を引いて立ち上がった。
「アイリス先生、少しいいかしら」
声をかけると、アイリスはすぐに顔を上げた。
「ええ、どうしました?」
ミモザは、机の上のプリントを数枚持って、歩み寄る。
「……アスターくんの件なんだけど」
その名前を出した瞬間、アイリスの表情がわずかに引き締まった。
「噂になっている、という話ですね」
「ええ」
ミモザは、持ってきた紙を机に置く。
「根拠はないの。でも、クラス内の空気が……よくない」
アイリスは、紙にざっと目を通す。
感情は、表情には出さない。
ただ、視線だけが少し鋭くなる。
「……集団の不安は、放置すると暴走します」
それは、経験に裏打ちされた言葉だった。
「ええ。だから……」
ミモザは、一瞬、言葉を選ぶ。
「念のため、生活状況の確認をした方がいいかもしれないと思って」
「生活状況?」
「持ち物とか、行動とか……
極端な例だけど、“危険なもの”を持ち込んでいないか、とか」
そこまで言って、ミモザは気づいた。
自分の言っていることが、
どれだけアスターを疑う前提に立っているか。
それでも、言葉を止めなかった。
止められなかった。
アイリスは、少し考えるように視線を落とす。
数秒の沈黙のあと、口を開いた。
「……抜き打ちの持ち物確認、ということですか」
ミモザの喉が、わずかに鳴る。
「“検査”とまでは言いたくないけど……
でも、結果的には、そうなるわね」
アイリスは、すぐには答えなかった。
ただ、机に指先を軽く置いたまま、静かに言った。
「もし、何も出なかったら?」
「……そのときは」
ミモザは、目を伏せる。
「私たちが、彼を傷つけたことになる」
職員室の空気が、わずかに重くなる。
「でも」
アイリスが、淡々と続けた。
「もし、“何か”が出てしまったら?」
その「何か」が、具体的に何なのか。
二人とも、はっきりとは想像していない。
ただ、
“普通ではない何か”
という漠然とした不安だけが、そこにあった。
「……保護者への連絡は、避けられませんね」
アイリスの言葉は、事務的だった。
だからこそ、現実味があった。
「ええ……」
ミモザは、小さく頷く。
その瞬間、決定してしまった。
もう、引き返せない。
「時期は……」
「クラスが落ち着く前にやった方がいいでしょう」
アイリスは、カレンダーに視線を落とす。
「……今週中が、妥当ですね」
今週中。
それはつまり――
あと数日以内に、アスターのカバンの中身が、誰かに見られるということ。
ミモザの胸に、嫌な感覚が広がった。
正しいことをしているはずなのに、
どこかで、取り返しのつかない一線を越えた気がした。
それでも、教師という立場は、
もう決定を取り消すことを許してくれない。
「……わかりました」
ミモザは、静かに答えた。
職員室の外では、
今日も何事もなかったかのように、生徒たちの笑い声が響いている。
その中に、
これから“調べられる側”になる少年がいるとも知らずに。