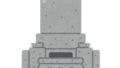気が付けばメンバーの全員が寝ていて朝を迎えていた。
昨夜のことをはっきりと覚えている者もいれば、ぼんやりとしか覚えていない者もいた。
ティーパンに言わせれば、ここのところずっと気を張りっぱなしだったからいい羽伸ばしになったんだそうだ。
昨夜のご飯の残りを食べながら今後の方針を決める。
「重要なのは、この世界から抜け出すための何かを探すために先に進むか、とりあえずここまでの道を戻って探すかだね」
ティーパンが相変わらず謎のステーキを食べながら言う。
「それを決めるのはもちろん勇者。きみだ」
フォークに刺したステーキから血が滴り落ちる。
そのフォークをずいっと助態に向けながらティーパンが言う。
相変わらず方針を決めるのを助態に任せる。
「今戻れば、ここまでの間にその何かがあるかどうかがはっきりする。もしも今まで通った道にその何かがあった場合、戻らなければ探す範囲が増えるってことですよね?」
「そゆこと。ただし、この先にその何かがあるならば戻るのは無駄に終わる。それにその何かがなんなのかが不明なのも問題だ」
むしり。とティーパンがステーキを噛みちぎる。
「んー。それならとりあえず進めるところまで進んで、怪しそうな場所だけ覚えておいて、もしもその何かが見つからなかったらその怪しい場所を探すって方法でどうですか?」
「私は勇者が決めたことなら文句はないよ」
「私も賛成です」
ティーパンの隣で温かい飲み物を飲んでいた純純が賛成した。
「アタイもいいよ」
謎の焼き魚を骨ごと食べながらもふともも賛成した。
どうやら反対する者はいないようだ。
「今のところ怪しい場所は、あの金属の部屋かしら?」
アンアンが再確認する。
「カーテンがあったという部屋は全部見たのか?」
ちあが問う。
ちあはモンスターに捕らえられていたので、カーテンの間を見ていない。
あの時は、助態がちあを助けるために部屋の隅々まで怪しいところをチェックしている。
「カーテンの部屋には、この世界を抜け出す何かはないな」
そのことを思い出しながら助態が言う。
特に怪しいものは確かになかったし、全てのカーテンを開けている。
「最初の絵画の部屋はどうかしら?」
くびちが言う。入り口からすぐの間のことだ。
「あー。そんなに入念にチェックはしてないっすねー」
そういえばと思い出しながらぱいおが言う。
「今のところ、絵画の部屋と金属の部屋が怪しいってこったね」
もふともがボリボリと、魚の骨を音を立てて食べる。
「あのー、怪しいと言えばここの宿はどうですか?」
ルブマがもっともなことを言う。
お風呂に寝床、食事まで用意されている場所だ。怪しさこの上ない。
「さくっと調べてみたけど、怪しそうなものはなかった。なんで食事が用意されているのかは不明だけどね」
すでにティーパンは、この宿を調査していたようだ。
「それじゃあ、食事を済ませたら先に進みましょ?」
ティーパンの行動に少々驚かせながら、アンアンがみんなに促した。
こうして全員が食事を終えると謎の宿を後にした。
●
宿を出て先に進むと迷路のような部屋が現れた。
迷路というには少々表現が違うかもしれない。
基本的には一本道だ。
しかし、道の途中に複数の細い道が枝分かれしており、枝分かれした道は謎の扉へと続いていた。
更に枝分かれした道は全て上下へ続く小さな階段になっている。
「こいつは厄介だねぇ」
ティーパンがため息混じりの声を出す。
全ての扉を開けないと、この幽霊城から出るための何かを見つけられないかもしれないと思うと、助態も途方に暮れるしかなかった。
「片っ端から開けるのかい?」
ポリポリと後頭部を掻きながらもふともが問う。
「さすがにこれ全部を開けるのは大変ですよね?」
助態がティーパンに聞くと、ティーパンは肩をすくめてそれに答える。
「決めるのは勇者。きみだ」
助態には何となく、どの扉も無意味な扉に思える。
「俺はただ真っすぐ進めばいい気がします」
「私もそんな気がします」
驚いたことに純純もそれに賛同した。
「勇者とヒロインねぇ」
ティーパンだけがなぜか納得していた。
こうしてメンバーは真っすぐ進んで大きな扉を開けた。
●
扉の先はさっきよりも複雑な迷宮になっていた。
道はもう一本道ではなく、上下左右に道が枝分かれしていた。
「さっきのはこれのデモンストレーションってことかしら」
くびちがうんざりしたように言う。
「勇者様……」
助態の隣で純純が不安そうに言う。
「あぁ……」
その言葉に助態は生唾をゴクリと飲み込んで答える。
「君たちには何かが見えているのかい?」
その様子にティーパンが疑問を投げかける。
先ほどの部屋から、助態と純純だけ他のメンバーとは違う空気を感じ取っていた。
いや、正確にはこの幽霊城に来た時も、別世界なのか別の場所かで2人だけは違う感覚を持っていた。
「もしかしてこの城は、勇者とヒロインを覚醒させるのか?」
ブツブツとティーパンが呟く。
「何かが見えているわけではないのですが」
そんなティーパンに向かって助態が先ほどの質問に答える。
「この迷路はヤバい雰囲気がします」
「君たちはさっきから感覚がかなり鋭くなっているはずだ。きみたちの感覚を私たちは信じよう」
こうして助態たちは、助態と純純を先頭に階段の迷宮を進むことになった。
最初の分かれ道だ。真っすぐ進む道と上下に階段の3択。
「「せーの」」
助態と純純が同時に声をかけて指を指す。
2人が指した先は下に降りる階段。
「他のみんなはどの道が正解だと思う?」
直感でいいから。とティーパンが言うと、誰も下を選ばなかった。
「助態と純純には何か特別な力でも備わっておるのかの?」
ちあがティーパンに問うが、ティーパンもその実よく分かっていない。
「勇者とヒロインは直感力が優れていると聞く。今までもたまにその片鱗は見せていただろ?」
それでティーパンは助態に物事を決めさせていたのだ。
「それにしてもこの迷路。扉の先にはどんなものがあるんだい?」
もふともが助態に聞くが助態は首を横に振る。
「何か罠がありそうな気はします」
助態の隣で純純が言う。
「わなぁー?」
そんな馬鹿なという声をもふともが出す。
「この城に罠があるとして、普通はこの城に侵入させないために罠を張らないか?」
ティーパンが疑問を投げる。
「脱出を防ぐために罠は仕掛けないってことですか?」
助態がそれはどうだろう。という言い方で聞き返す。
「あぁ。脱出を本気で防ぎたいなら罠よりも強力なモンスターを配置すればいい」
確かにティーパンの言う通り、脱出を防ぐならばかかるか分からない罠よりもモンスターに守らせた方が効率がいい。
侵入を防ぐならば、罠があることで侵入をためらうことも考えられる。
「ゲームのような感覚で脱出の難易度を上げるために罠を作るなら分かりますけど、現実的に難易度を上げる意味がありませんもんね」
助態が現実世界でのゲームを思い浮かべながら言う。
あくまでも遊ぶ側が楽しめる程度に難易度が上がるなら、脱出を防ぐ罠があるのは理解できる。
しかし本当にこの城から抜け出せなくさせたいならば、罠なんか仕掛けるよりも脱出不可能な状態にした方がいいし、そもそも城に侵入させなければいい。
「そこでだ、私の見解だが」
ティーパンが人差し指をビッと立てる。
「この城が別の空間だという君たちの感覚が正しいと仮定しよう」
君たちと言って助態と純純を指さす。
「それならばこの城に侵入するのを阻止させる必要はない。侵入することが簡単に言えば罠だからだ」
別の空間に飛ばす罠という意味だろう。
「そしてこの異様な部屋。これも君たちの感覚が正しいならば罠が張り巡らされているということだ。それはつまり、この城の中に留めることで何かメリットがあるということだろう」
「つまりどういうことっすか?」
ぱいおが困惑したような顔をする。
「つまりじゃ。敢えてこの城の中に獲物を侵入させ、この城の中で捕獲をして何らかのメリットを得ているというわけじゃ」
ちあがティーパンに代わって説明をすると、もふともが冗談じゃないという声を出す。
「おいおいおいおいー。やだよぅ? 獲物なんて物騒な物言い。それにメリットって何だい?」
「吸収か……」
もっこりがボソリと言った。
「ん。ちあもそう思うのじゃ」
「なるほどな。それならあの宿で食事が用意されていたのにも納得だな」
どうやらもっこりはティーパンとちあの考えに付いてこれているようだ。
「どういうこと?」
しびれを切らしてくびちが問う。
「この城はモンスターの可能性が高いってこと。人喰いの経験を思い出してごらん」
ティーパン言葉に助態も納得した。
「だからこの城には誰も近づかなかったのか」
はあはあも納得したようだ。
「でも逆に言えば、この異様な部屋がこの先に出口があることを物語っている。よかったな。前の部屋にはこの空間から出る何かはないだろう」
ティーパンがにぃ。と笑った。
確かにこの階段の間にこれだけ進むのを拒む罠が張り巡らせているということは、幽霊城はこの先に進ませたくないという意思の現れだろう。
つまり、この先に出口に繋がる何かがあると考えてよい。
メンバーは周囲に気を付けながら、下へと降りる階段へ向かった。
その先には真っ赤な扉がある。
●
扉の先には、似たような階段の迷宮が広がっていた。
「またかい」
もふともがうんざりしたように言う。
「ここは、さっきと別の場所かい?」
ティーパンが助態と純純に問う。
「いえ、さっきと同じ部屋だと思います。扉から別の扉に移動したのだと思います」
キョロキョロと辺りを見渡しながら助態が言う。
「正解の扉を選ばないとこの部屋に戻されるのか……」
ティーパンが舌打ちをすると、それを純純が否定した。
「いえ、正解の扉でもこの部屋に移動します。扉から扉を通って少しずつゴールに向かうイメージです」
「へぇー階段と扉の迷路ってわけか」
ティーパンが長く口笛を吹く。
「それにしてもよく正解の行き先とか分かるわね。私にはさっきの部屋とこの部屋が同じなのか違うのかも分からないわ」
アンアンが驚きと尊敬の入り混じったような声を出す。
「それが勇者とヒロインの特性なんだろうね」
ティーパンが言うには、勇者とヒロインは感覚が鋭くなるという。直感力とも言える力のせいなのか、2人はことごとく正解の扉を選んで行った。
「本当に正解の道なんかい?」
あまりにも長い道のりを歩いていることにもふともが疑問を抱く。
「正直、これが正解かどうかは分からない」
助態が正直に答える。
事実、今の道が本当に正解かなんて誰にも分からないし、何度か同じ場所にも戻ってきていた。
それでも助態と純純には、少しずつでも前進している感覚があった。
根拠はないが、それこそが2人の特性なのだろう。
そしてついに……
「出口だ」
誰が口にしたのかは分からないが、みんなが思ったことだ。
何時間も歩き続けようやく階段の間の出口にたどり着いた。
助態が扉に手をかけた――