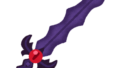夏休みに入ると、いつもとは違ったリズムに勇者は戸惑っていた。
いつも決まった時間に起きていたので、この日も同じ時間に起きて朝食を済ませると、やることがないことに気がついた。
『暇だ』
勇者の夏休みは、暇で退屈な時間から始まった。
しかし――
すぐにみゆうからお誘いが来る。
『みゆうか……気が乗らないな……』
「ごめん。今日はれんやともやと約束があるから」
そう返事を送り、みゆうからの誘いを断った。
この日は結局、暇つぶしに近所のみずほと街をブラブラして終わった。
「みずほって夏休みなんか予定あんの?」
勇者が帰り際に、ふとした疑問を投げかけた。
「ないよ?」
勇者はこの言葉を聞いて、少しほっとしたのだった。
「明後日は祭りの約束忘れんなよ」
みゆうからの連絡に、分かってる。と勇者は返事をしてそのまま眠りについた。
●
祭り当日――
勇者は30分も早く待ち合わせ場所に到着していた。
祭りが楽しみでしょうがなかったのだ。
想像以上の人混みにやや緊張しながらみゆうを待っていると、間もなく浴衣姿のみゆうが現れた。
まだ15分前なのを考えると、みゆうもこの祭りを楽しみにしていたのだろう。
それにとても綺麗だ。
勇者は素直にそう思った。
「おい」
開口一番にみゆうが不機嫌そうな声を出す。
あれ? と勇者が予想外のみゆうの反応に戸惑っているとみゆうが照れ臭そうに笑った。
「まずは浴衣を褒めろよ。どうだ? 可愛いか?」
「うん。とても似合ってる。可愛い」
その言葉にみゆうは両頬を赤く染めた。
この言葉は紛れもない勇者の心からの真実の言葉。
実際、色白で明るいロングの茶髪を一つにまとめて淡い水色のシュシュで留め、同じく淡い水色と薄紫の紫陽花模様の浴衣を着たみゆうは誰よりも綺麗だった。
「行こっか」
にこりと微笑んでみゆうが片手を差し出す。
もはやいつもの慣れた行動。
その手を黙って勇者が取り、2人手をつないで人混みの中を歩く。
「多分ねー。ゆーた達もいると思うけど、今日は合流する気ないから」
イカ焼きを頬張りながらみゆうが言う。
「そうなの? なんで?」
見事にみゆうがゲットした射的やヨーヨー釣り、金魚すくいの景品を持ちながら勇者が訊く。
「だって祭りだよ? せっかくの2人きりだよ? ダブルデートやトリプルデートなんてして気を使うのダルいじゃん」
ずいっと勇者の顔の近くまで顔を寄せながらみゆうが言う。
「そっか。ダブルデートやトリプルデートって邪魔って感覚もあるんだ」
「そ」
そう言いながら最後の一口を食べる。
「勇者は何にも食べないの?」
勇者の手からわたあめを取りながらみゆうが訊ねる。
「食べたいのとか、ない?」
小首を傾げる。
ドキン――
勇者の心臓が跳ねる。
「や……焼きそばかな」
「えー! さっき通り過ぎちゃったよー。ちゃんと言ってよねー」
頬を膨らませるその表情すら、勇者には可愛く見えていた。
「勇者ってさ」
勇者にわたあめを渡し、勇者より少し前に進みながらみゆうが言う。
そのまま両手を後ろに組んでくるりと振り返る。
「いつもうちのこと優先してくれるよね。それってさ、うちのこと好きってことで合ってる?」
にこりと微笑む。
ほっぺに少しわたあめがついているところがまた可愛いと、勇者は感じてしまった。
「好き……かは分からないけど可愛いし一緒にいて楽しいと思う」
そう言いながら勇者はみゆうのほっぺのわたあめをハンカチで拭く。
「ありゃ。食べてもよかったのに」
ニヤリとみゆうが笑うと、勇者が顔を真っ赤にした。
「えぇ!? それは無理!」
「なぁーんで無理なんだよー! うちとはキスできないってか?」
みゆうが勇者の肩を組みながら、自分の食べかけのわたあめを無理やり食べさせようとする。
「もがもが」
「ほぅーら。間接キスだ」
にしし。と満足そうにみゆうが笑う。
「全く。いつも強引なんだから」
その言葉にみゆうが、ぷっ。と吹き出す。
「うちもさ。勇者といると楽しいよ。その感情って好きって感情とは違うものなのかな?」
吹き出した後にみゆうが真面目な話しをする。
「そんなのわかんないよ……」
「そっか……」
勇者の返答に、みゆうは寂しそうな顔を見せたが、勇者は気がつかなかった。
丁度花火が上がったからだ。
●
「綺麗だ……」
花火を見上げてポツリと勇者が呟く。
そんな勇者の横顔を眺めながらみゆうが問う。
「何あんた。花火見たことないの?」
「小さい頃に親と見たことはあるけど、少なくとも小学校高学年くらいから全くないかな」
相変わらず花火を見上げたまま勇者が答える。
みゆうの方を見向きもしない。
その様子にみゆうが少し膨れるが、見向きもしない勇者には効果が全くなかった。
「来年も一緒に来よう」
唐突に勇者が言う。
珍しかった。
勇者からデートに誘うことは一度もなく、間違いなく初めてのお誘いだった。
勇者は、素直に一緒にいれて楽しいと感じていた。
「うん」
みゆうは、目の端の涙を拭いながら答えた。
ただの口約束。確約でもなんでもない。気まぐれかもしれない。それなのに――
なぜかみゆうの目からは涙がどんどん溢れてくるのだった。
花火に夢中の勇者は、そんなことつゆ知らず、夜空に咲いては散る花火を心の底から美しいと思い、幻想にふけっているのだった。
●
「口あけすぎ」
ポカンと口を開けて花火を見ている勇者に向かって、みゆうが笑いながら言う。
「え! 俺夢中になってた? やべ! なんか俺に話しかけてた?」
慌てる様子を見てみゆうはぷっ。と再び吹き出す。
「さっきのうちが馬鹿みたいだからやめて」
「? 何のこと?」
「うっさい。さ、行くよ」
勇者の手を取りみゆうが引っ張る。
「お。おい。引っ張るなよ。花火まだ終わってないよ? 最後まで見ないの?」
みゆうは勇者の言葉を無視して、どんどん歩き続ける。
『彼女。って立場を利用しているのはうちなんだよな……』
みゆうはとある決意を胸に秘めていた――
色とりどりの景色が足早に去っていく。
その光景すらも勇者は美しいと思えていた。
花火の音は遠ざかり、祭りの喧騒も少しずつ静かになっていく……
綺麗な灯かりが後ろへと流れていき、少しずつ日常の夜へと戻って行った。