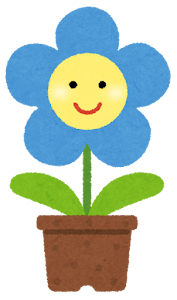朝の教室は、まだ眠っているみたいに静かだった。
机に鞄を置いて、俺は席に座る。
いつもなら、そこからスマホを眺めるか、ぼんやり時間を潰すか。
最近は――ノートを確認するか。
机の中に手を入れ、指先でノートの端に触れる。
開くか、開かないか。
その一瞬の迷いが、ここ数日ずっと続いていた。
「……おはよ」
声がして、顔を上げる。
ダリアだった。
いつも通りの制服。
いつも通りの表情。
いつも通りの距離感。
なのに、どこか「来るとわかっていた」気がした。
「おはよう」
「早いね」
「そっちこそ」
軽い会話。
ごく普通のやり取り。
ダリアは俺の前の席に座ると、くるりと振り返った。
「……今日、もう見た?」
「なにを」
「ノート」
声は小さい。
周りに誰もいないことを、ちゃんと確認した声だった。
「……まだだよ」
「そっか」
それだけ。
責めるわけでもなく、強く言うわけでもなく。
ただ、それだけだったのに。
俺は、机の中に入れていたノートを、少しだけ手前に引き寄せていた。
それに気づいたのは、ダリアが視線を落としたときだった。
「……開かなくていいよ、別に」
彼女は、あくまで自然な声で言った。
「今すぐじゃなくても」
「……だったら」
「でも、後で見ておいてね」
言い方が、柔らかすぎて、拒否しづらい。
「今日、何も書いてなかったら」
「……」
「それはそれで、ちょっと安心できるから」
“安心できる”。
また、その言葉だった。
「ダリアは……」
ふと、口をついて出た。
「そんなに、気になるのか」
ダリアは一瞬だけ考えるように視線を上げて、それから小さく頷いた。
「うん。気になるよ」
「……どうして」
「だって……」
言葉を選ぶみたいに、ほんの少し間を置いて。
「アスターくんが、一人で抱えてるものを」
「私だけは、知ってるって思っちゃったから」
それは、誇っているようにも。
責任を感じているようにも聞こえた。
「知らなかった頃には、戻れないでしょ」
「……」
「だったら……せめて、ちゃんと“共有”していたいなって」
共有、という言葉が、静かに落ちる。
「秘密も」
「不安も」
「安心も」
どれも、優しい言葉だった。
なのに、その中に、わずかな違和感が混じっていた。
「……俺の負担を、増やしてないか?」
「え?」
「気にしすぎると……ダリアのほうが、しんどくなるだろ」
正直な言葉だった。
ダリアは少し驚いた顔をしてから、ふっと笑った。
「……優しいね」
「そういう意味じゃなくて」
「ううん、いいの」
そう言って、ダリアは首を横に振る。
「私がしんどくなるかどうかは」
「私が決めるから」
やわらかい声だった。
でも、言い切りだった。
「アスターくんが気にすることじゃないよ」
「……」
「むしろ、気にしてくれるほうが……ちょっと困る」
困る。
その言葉の意味が、すぐには理解できなかった。
「だって」
ダリアは、ほんの少しだけ目を細めた。
「それって、また“一人で背負おうとしてる”ってことになるでしょ?」
胸の奥を、正確に突かれた。
「……」
「だから、いいんだよ」
「私が勝手に関わってるだけだから」
勝手に。
でも、その言葉とは裏腹に、表情はどこか満足そうだった。
「ねえ」
ダリアは、俺の机の中に視線を落としたまま言った。
「今日の帰り、少しだけ時間ある?」
「……どうして」
「もしよければでいいんだけど」
視線が、俺の顔に戻る。
「一緒に、見たいなって」
何を、とは言わなかった。
でも、答えはひとつしかなかった。
ノート。
俺の選択。
俺の予測。
俺の罪。
「……考えさせてくれ」
「うん」
ダリアは、あっさり頷いた。
「待つのは、慣れてるから」
その言い方が、少しだけ引っかかった。
まるで、
もう何度も待ってきたことがあるみたいな。
チャイムが鳴り、教室が少しずつ騒がしくなっていく。
ダリアは前を向き、何事もなかったように授業の準備を始めた。
その背中を見ながら、俺は机の中のノートに指先を伸ばす。
まだ、開いていない。
でも、もう――
「いつ開くか」じゃなくて
「誰と開くか」を考えている自分がいた。
そのことに気づいたとき、
胸の奥で、また小さく、何かが引っかかった。