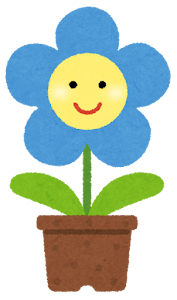放課後の空気は、昼間よりもずっと重かった。
教室には、俺とダリアだけが残っている。
誰かの気配があるわけでもないのに、やけに周囲を意識してしまう。
「……本当に、少しだけだぞ」
そう言うと、ダリアは小さく頷いた。
「うん。わかってる」
声は落ち着いている。
無理に踏み込もうとする様子もない。
だからこそ、逃げ道を失っている気がした。
机の中から、ノートを取り出す。
何度も触ってきた表紙。
何度も守ってきた重さ。
それを、今は机の上に置いている。
「……全部は見せない」
「うん」
「未来の詳細も、全部は書いてない」
「うん」
ダリアは、ただ聞いている。
促すでもなく、焦らすでもなく。
ただ、待っている。
その態度が、逆に怖かった。
ページをめくる。
最近書いた中で、いちばん“軽い”内容の頁。
誰かが困りそうだった出来事と、それを回避した結果。
名前も、出来事も、曖昧に書いてある。
完全な真実ではない。
でも、嘘でもない。
「……これだけだ」
ノートを、ダリアのほうに少しだけ滑らせる。
彼女は、すぐには手を伸ばさなかった。
一度、俺の顔を見る。
「……触ってもいい?」
「……ああ」
それだけで、胸の奥が少しざわついた。
ダリアは、そっとノートの端に指をかけた。
乱暴さは、まったくない。
まるで、壊れやすいものに触れるみたいに。
視線が、ページの上をゆっくりなぞる。
文字を追う速度が、思っていたよりもずっと丁寧だった。
時間が、やけに長く感じる。
「……これ」
しばらくして、ダリアが小さく声を出した。
「この日付……」
「何か問題か」
「ううん。ただ……」
少しだけ、言葉を探す間があった。
「この日、本当に……何も起きなかったんだよね?」
「ああ。書いてある通りだ」
ダリアは、もう一度ページを見る。
それから、ほんのわずかに眉を下げた。
「……そっか」
それは、安心の表情だった。
でも同時に、どこか残念そうにも見えた。
「……なにか思ったのか」
思わず聞く。
ダリアは、首を横に振った。
「ううん。ただ……」
「こうやって見ると……ちゃんと“現実”なんだなって思って」
「……現実?」
「うん。アスターくんが、作り話をしてるわけじゃなくて」
「本当に、“これ”と一緒に生きてるんだって」
その言い方が、少しだけ引っかかった。
「……重いだろ」
俺は言った。
「見るだけでも」
ダリアは、一度だけ瞬きをして、それから小さく微笑った。
「……うん。思ってたより、ずっと」
でも、その声は震えていなかった。
「でも……」
ページから視線を外さないまま、続ける。
「だからこそ、見せてくれてよかったって思う」
「……どうして」
「だって」
そこで初めて、ダリアは顔を上げた。
俺を、まっすぐ見て。
「これを見ないまま、そばにいるのは……」
「ちょっと、ずるい気がしたから」
ずるい。
その言葉の意味が、すぐには掴めなかった。
「アスターくんだけが、知ってて」
「アスターくんだけが、決めてて」
「私は、ただ“理解してるつもり”だったでしょ?」
たしかに、その通りだった。
「それって……」
ダリアは少し考えるように間を置いてから言った。
「ちゃんと向き合ってるとは、言えない気がして」
理屈は、正しかった。
だからこそ、胸の奥が妙にざわつく。
「……これ以上は、見せない」
改めて言う。
ダリアは、あっさり頷いた。
「うん。約束だからね」
素直すぎる反応だった。
拍子抜けするほどに。
ダリアはノートを俺のほうに戻すと、指先をゆっくり離した。
「……ありがとう」
「なにが」
「信じてくれたこと」
それは、あまりにもまっすぐな言葉だった。
「少しだけでも、見せてくれたってこと」
「……」
「それって、私にとっては……すごく大きいから」
その言い方が、妙に重かった。
「……大げさだろ」
「大げさじゃないよ」
ダリアは、静かに言った。
「だって、これって……」
「アスターくんの“世界”の一部でしょ?」
世界。
その言葉に、背中がひやりとした。
ただのノートのはずなのに。
ただの記録のはずなのに。
それを、彼女は“世界”と言った。
「……もういいだろ」
俺はノートを閉じて、鞄にしまった。
それ以上、触れられたくなかった。
「うん。十分」
ダリアは、穏やかに笑った。
「今日は、これでいい」
今日は、という言い方が、ほんの少しだけ引っかかる。
「じゃあ、帰ろうか」
「……ああ」
二人で教室を出る。
廊下を並んで歩きながら、ダリアはいつもと同じ調子で話していた。
好きな授業のこと。
部活の話。
くだらないクラスメイトの噂。
何も変わっていないように見える。
でも――
「……ねえ、アスターくん」
校門の前で、ダリアが言った。
「なに?」
「今日見せてもらったところ」
「……」
「ちゃんと、覚えておくね」
それは、優しい言葉だった。
感謝の言葉のはずだった。
なのに。
「……覚えなくていい」
反射的に、そう言っていた。
ダリアは、一瞬だけ目を丸くしたあと、小さく笑った。
「……そっか」
「でもね」
やわらかい声のまま、続ける。
「私は、忘れないと思う」
それだけ言って、ダリアは手を振った。
「じゃあ、また明日」
いつも通りの笑顔。
いつも通りの別れ方。
なのに、その背中を見送りながら、胸の奥に、消えない違和感が残った。
――一頁だけ、見せただけのはずなのに。
――どうしてこんなに、取り返しのつかないことをした気がするんだろう。
鞄の中で、ノートの重さが、さっきよりもずっと重く感じられた。