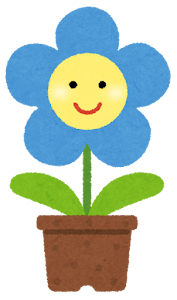放課後の廊下は、静かだった。
窓の外から部活の掛け声が遠く聞こえるだけで、
校舎の中は、まるで時間が止まったみたいに静まり返っている。
アスターは、階段の踊り場で足を止めた。
「ねえ」
背後から、よく知った声がする。
振り返らなくても分かる。
この距離、このタイミング、この余裕。
ダリアだ。
「さっきさ」
彼女は、軽い足取りで近づいてくる。
「スズランと、話してたでしょ」
アスターの喉が、わずかに鳴った。
「……見てたのか」
「見てたよ」
即答だった。
ダリアは、踊り場の手すりにもたれ、夕陽を背にする。
「ずいぶん長かったじゃん。
ああいうの、あの子すごく苦手なのに」
「……」
アスターは、何も言えない。
ダリアは、彼の沈黙を楽しむように、くすっと笑った。
「で?」
視線が、まっすぐ突き刺さる。
「どこまで話した?」
「……核心は、何も」
「ふーん」
その返事に、ダリアは首を傾げた。
「じゃあ、逆に聞くね」
声が、少しだけ低くなる。
「アスターは、あの子が“気づいてない”と思ってる?」
胸の奥が、ぎゅっと締めつけられる。
「……勘づいてはいると思う」
「でしょ?」
ダリアは、満足そうに笑った。
「もう、とっくに気づいてるよ。
ノートの中身までは知らなくても、
“何かがおかしい”ってことくらい」
アスターは、思わず一歩後ずさる。
「……どうして、そんなに断言できる」
「だって」
ダリアは、人差し指で自分のこめかみを軽く叩いた。
「スズラン、観察型だもん。
しかも、アスターのこと限定で」
その言葉は、妙に生々しかった。
「目線。距離。沈黙の長さ。
全部、拾ってる」
「……」
「今日の質問もさ」
ダリアは、楽しそうに続ける。
「“聞いてないふりして、全部聞く”やり方だったでしょ」
アスターの脳裏に、放課後の会話が蘇る。
――危ないことじゃないよね?
――ちゃんと一人で決めてる?
あれは、探りだった。
「ねえ」
ダリアは、一歩近づく。
「怖くない?」
「……何が」
「スズランが、真実に近づくこと」
その距離は、近すぎた。
でも、触れない。
触れないからこそ、逃げ場がない。
「彼女はさ」
ダリアは、囁くように言う。
「止めるよ。
泣いて、怒って、説得して」
「……」
「それでも止まらなかったら」
ダリアの声が、少しだけ冷たくなる。
「壊れる」
その一言が、重く落ちた。
「アスターは、どっちがいい?」
「……」
「スズランが壊れるのと」
一拍、間を置く。
「世界が壊れるのと」
アスターは、目を伏せた。
選択肢は、最初から残酷だった。
「安心して」
ダリアは、くるりと背を向ける。
「まだ、何も言うつもりはないから」
「……本当か?」
「うん」
彼女は、振り返らずに言った。
「だって、面白くなるのはこれからでしょ?」
その言葉に、感情はなかった。
期待だけが、あった。
「ただし」
ダリアは、最後に足を止める。
「スズランが“自分で”辿り着くなら」
ちらりと、横顔だけを向ける。
「それは、それでアリかなって」
そう言って、彼女は階段を下りていった。
一人残されたアスターは、拳を強く握る。
(……詰んでる)
止めても、壊れる。
止めなくても、壊れる。
そして、ダリアだけが、
その過程を楽しむ立場にいる。
遠くで、下校のチャイムが鳴った。
その音は、
これから始まる“崩壊”の合図みたいに聞こえた。