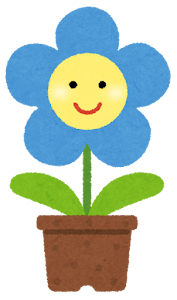ダリアは、ノートを見なかった。
正確に言えば――
見なくても分かった、という顔をした。
「そのページ、閉じるの早すぎ」
放課後の教室。
窓の外はオレンジ色に傾いているのに、彼女の声だけが妙に冷たい。
「……何の話だよ」
俺はノートを机の端に押しやった。
指先が、まだ震えているのが自分でも分かる。
ダリアは席に腰かけ、頬杖をついた。
いつもの軽い笑み。
でも、目だけが笑っていない。
「ねえアスター。さっき、書こうとしてたよね」
心臓が、嫌な音を立てた。
「書いてない」
「うん。書いてない」
その言い方が、逆に刺さる。
「でもさ。――“書きそうになった”」
ダリアは、ゆっくりと立ち上がった。
一歩。
また一歩。
距離が縮むたびに、逃げ道が消えていく。
「最近のあなた、分かりやすすぎ」
机の上のノートに、視線を落とす。
触れない。開かない。
ただ、そこに“ある”ことを確認するだけ。
「その反応。
赤い文字、いつもと違ったでしょ」
俺は答えなかった。
でも、それが答えだった。
「……名前」
ダリアが、ぽつりと言う。
「“書かないって決めてた名前”」
息が止まる。
彼女は俺を見ない。
窓の外でも、床でもなく――
俺の指先を見ていた。
「ペン、持つ手がさ。
今までで一番、迷ってた」
ぞっとした。
ダリアは、見える人間じゃない。
それなのに、選択の重さだけを正確に嗅ぎ取る。
「……誰だよ」
声が、ひどく低くなった。
ダリアは、少しだけ首を傾げる。
「それ、私が当てたらどうする?」
「――やめろ」
「ふふ」
小さく笑ってから、真顔になる。
「ねえ。
それ、スズランでしょ」
世界が、止まった。
否定する言葉は、いくらでもあるはずだった。
なのに、喉が動かない。
ダリアは、俺の沈黙を楽しむように眺めてから、続ける。
「違ってたら、ごめん。
でもさ……」
一歩、さらに近づく。
「“一番書きたくない名前”って、
一番助けたい名前でもあるんだよね」
机の上のノートが、やけに遠い。
「アスター。
あなた――もう、逃げられないところまで来てる」
「……黙れ」
「黙らないよ」
ダリアは、はっきりと言った。
「だって、ここからが一番面白いんだもん」
その言葉に、悪意はなかった。
ただの事実を述べているだけの声。
「書く?
それとも、見殺しにする?」
どちらも、地獄だ。
「どっちを選んでも、
あなたは“選んだ人”になる」
ダリアは、俺の横をすり抜け、出口へ向かう。
振り返らずに、最後に一言。
「ちなみに」
ドアの前で立ち止まり、微笑んだ。
「私なら――
書くね。後悔する方が、長く楽しめるから」
扉が閉まる。
教室には、俺とノートだけが残った。
ページを開けば、
あの名前は、もう隠れてくれない。
それでも俺は、
まだペンを置いたままだった。