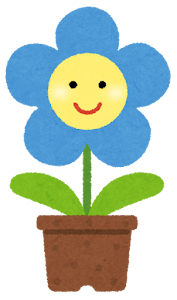放課後の中庭は、思ったより人が少なかった。
部活に向かう生徒たちは校舎の裏へ流れていき、
残るのは、帰りそびれた数人だけ。
スズランは、花壇の縁に座っているダリアを見つけた。
制服のスカートを気にも留めず、
スマホを眺めながら、暇そうに足を揺らしている。
「……ダリア」
声をかけると、彼女はゆっくり顔を上げた。
「あ」
それだけ。
驚きも、警戒もない。
「なに? スズラン」
その自然すぎる反応が、逆にスズランの胸をざわつかせた。
スズランは、ダリアの前に立つ。
「ちょっと、話したい」
「いいよ」
即答。
まるで、最初からこの瞬間を待っていたみたいに。
ダリアは立ち上がり、花壇から降りた。
「ここでいい?」
「……うん」
夕方の風が、二人の髪を揺らす。
少し、沈黙。
先に口を開いたのは、スズランだった。
「最近さ」
言葉を選ぶ。
「アスターと、やけに距離近くない?」
ダリアは、きょとんと目を瞬いた。
「そう?」
「そう」
スズランは、はっきり言った。
「話してなくても、近い。
見てなくても、分かってる感じがする」
ダリアは、ふっと笑う。
「あー……それ?」
軽い。
あまりにも軽い。
「仲良いだけじゃない?」
「違う」
スズランは、首を振った。
「“仲良い”じゃない」
ダリアの笑みが、ほんの少しだけ薄くなる。
「じゃあ、なに?」
試すような声。
スズランは、一歩踏み出した。
「共犯、みたい」
一瞬。
本当に一瞬だけ、ダリアの目が細くなった。
でも、すぐに元の表情に戻る。
「物騒だね」
「うん」
スズランは、誤魔化さなかった。
「自分でも、そう思う」
胸の奥が、きゅっと締まる。
「でもさ……あのノート」
ダリアの視線が、ぴたりと止まる。
「アスターがずっと持ってる、それ」
スズランは、ダリアの反応を見逃さなかった。
ほんのわずかな沈黙。
ほんの一拍の間。
それだけで、確信に変わる。
「……やっぱり、知ってるんだ」
ダリアは、ゆっくり息を吐いた。
「スズランってさ」
声のトーンが、少し落ちる。
「鋭いよね。
優しいのに」
「はぐらかさないで」
スズランは、珍しく強い口調で言った。
「教えて。
あれ、何?」
ダリアは、しばらく黙っていた。
そして、肩をすくめる。
「言えない」
即答だった。
「……なんで」
「決まりだから」
「誰の?」
ダリアは、にっこり笑った。
「世界の」
その言葉に、スズランの背中が冷たくなる。
「ふざけてる?」
「全然」
ダリアは、真顔だった。
「むしろ、すごく真剣」
スズランは、拳を握る。
「ねえ、ダリア」
声が、少し震える。
「アスター、苦しそうだよ」
その言葉に、ダリアは首を傾げた。
「そう?」
「そうだよ」
「でもさ」
ダリアは、楽しそうに言う。
「彼、選んでるよ。
ちゃんと、自分で」
その言い方が、どうしても許せなかった。
「……選ばされてるんじゃないの?」
スズランは、踏み込む。
「ダリア、あんたが」
一瞬、風が止んだ気がした。
ダリアの笑顔が、完全に消える。
「それ以上言うと」
声は、静かだった。
「戻れなくなるよ」
スズランは、怯まなかった。
「もう、戻るつもりない」
はっきりとした答え。
「このまま見てる方が、無理」
ダリアは、じっとスズランを見る。
その視線は、観察者のものだった。
そして――
ゆっくりと、口角を上げる。
「いいね」
「……なにが」
「その顔」
ダリアは、楽しそうに言った。
「やっと、“当事者”になった」
スズランの胸が、どくりと鳴る。
「忠告しとくね」
ダリアは、近づいてくる。
「アスターを守りたいなら」
耳元で、囁く。
「優しさだけじゃ、足りない」
そう言って、彼女は離れた。
「それでも踏み込むなら」
振り返りざまに、ひとこと。
「壊れる覚悟、しといて」
ダリアは、そのまま歩き去った。
残されたスズランは、しばらく動けなかった。
(……やっぱり)
これは、ただの違和感じゃない。
誰かが、誰かを選び、
誰かが、切り捨てられる世界。
そして――
(……私も、もう外じゃない)
スズランは、夕焼けの校舎を見上げた。
踏み込んだ以上、
もう“知らなかった”とは言えない。