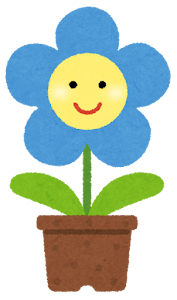スズランは、最近、ずっと胸の奥が落ち着かなかった。
理由ははっきりしている。
アスターの態度だ。
優しくなったわけでもない。
冷たくなったわけでもない。
ただ――
どこか、決めつけたような距離になった。
話しかければ応えてくれる。
でも、それ以上は踏み込ませない。
まるで、見えない線を引かれているようだった。
「ねえ、アスター」
昼休み。
席の横に立って、声をかける。
「……なに」
「最近、何か隠してない?」
言った瞬間、後悔した。
重すぎたかもしれない。
でも。
アスターの反応は、予想よりずっと分かりやすかった。
一瞬、動きが止まった。
ほんの一瞬。
でも、スズランには十分だった。
「……なんでそう思うんだ」
声は、平静を装っている。
けれど、どこか硬い。
確信に変わる。
「やっぱり、あるんだ」
笑おうとしたのに、うまくいかない。
「ねえ。私、信じられてない?」
アスターは答えない。
視線が、机の上から逸れる。
スズランは、その視線の先を、無意識に追った。
――机の中。
正確には、鞄の上。
何かを、気にしている。
「それ……」
指が、自然と動きそうになって、止めた。
勝手に覗くのは、だめだ。
それくらいの分別はある。
でも。
「見られたくないものがある」という事実だけが、
胸に、重く残った。
「ごめん」
スズランは、視線を戻した。
「変なこと聞いた」
「……いや」
短い返事。
でも、空気は戻らない。
「私さ」
少しだけ、言葉を選ぶ。
「……何も知らないのは、楽だと思ってた」
アスターが、わずかに顔を上げた。
「でも最近、ちょっと怖い」
正直な言葉だった。
「知らないまま、何かが決まってる気がして」
教室のざわめきが、遠く感じる。
「私のこと、
もう……決めてる?」
問いは、柔らかい。
けれど、その中身は、鋭かった。
アスターの表情が、ほんのわずかに歪んだ。
それが、答えに見えた。
「……スズラン」
名前を呼ばれる。
でも、その声は、どこか迷っていた。
「大丈夫だよ」
スズランは、先に言った。
自分に言い聞かせるように。
「どんな理由でも、
ちゃんと聞くから」
それは、約束でもあり、覚悟でもあった。
「だから――」
一歩、近づく。
その瞬間。
視界の端で、
また、あの“何か”が揺れた気がした。
見えないはずの、
触れられないはずのもの。
でも確かに、
空気が、ひりついた。
スズランは、思う。
これは、ただの気のせいじゃない。
アスターの周りには、
自分の知らない「何か」がある。
そして、それは。
――自分に関係している。
「……ねえ」
小さく、問いかける。
「私、
何から守られてるの?」
その言葉に、
アスターは、答えられなかった。