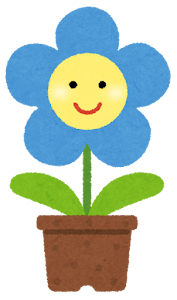スズランは、いつも通りだった。
「ねえアスター、卒業したらどうする?」
放課後の廊下。
部活帰りの生徒が行き交う中で、彼女だけがやけに穏やかな声をしていた。
「……急だな」
「急じゃないよ。もうすぐ三年だし」
スズランは歩きながら、鞄の紐を両手で持つ。
少し前かがみになる、いつもの癖。
「私さ、あんまり将来の夢とかないんだけど」
それを聞いた瞬間、
ノートの赤い文字が脳裏をよぎる。
――未確定。
――条件付き。
――分岐点、複数。
俺は何も言えなくなる。
「でもね」
スズランは楽しそうに続ける。
「高校出たら、ちゃんと一人暮らししてみたいなって思ってる」
「……一人で?」
「うん。最初は大変だろうけど」
彼女は笑った。
「失敗しても、生きてれば何とかなるでしょ」
胸の奥が、ぎゅっと締め付けられる。
生きてれば。
その言葉が、こんなにも重いなんて。
「それでさ」
スズランは立ち止まり、俺の方を向く。
「アスターは?」
「……俺?」
「将来。何するの?」
答えられなかった。
俺の将来は、
彼女の未来と、すでに絡みついている。
「決まってないならさ」
スズランは、少し照れたように視線を逸らす。
「同じ街にいられたらいいなって思うんだ」
息が止まる。
「偶然でもいいし。
たまたま電車で会うとか」
そんな未来は、
ノートには一度も出てこなかった。
「別に、約束とかじゃないよ?」
慌てて付け足す。
「ただ……想像すると、ちょっと安心するだけ」
俺は、彼女の顔を見られなかった。
見てしまったら、
“書かないと決めた名前”を思い出してしまう。
「ねえ」
スズランが、不思議そうに首を傾げる。
「最近、元気ない?」
「……そう見えるか」
「うん。前よりずっと」
少し困ったように笑う。
「私、アスターが黙ってる時の方が怖いんだけど」
――それは、知らないからだ。
俺が何を見て、
何を選ばされているかを。
「大丈夫だよ」
スズランは、何も疑わずに言った。
「どんな未来でも、
ちゃんと話せば何とかなるって」
その言葉は、
この世界で一番、残酷だった。
話してどうにかなるなら、
俺はもうとっくに話している。
でも――
「じゃあね」
スズランは手を振る。
「また明日」
その背中を、
俺は見送ることしかできない。
ノートを開けば、
彼女の未来は変えられる。
でも、変えた瞬間――
この“何も知らない笑顔”は、もう戻らない。
俺は、制服のポケットに入れたペンを握りしめた。
まだ、書いていない。
それだけが、
今の俺に許された唯一の逃げ道だった。